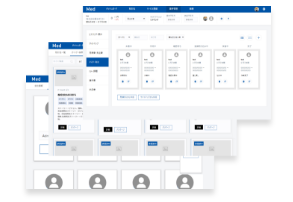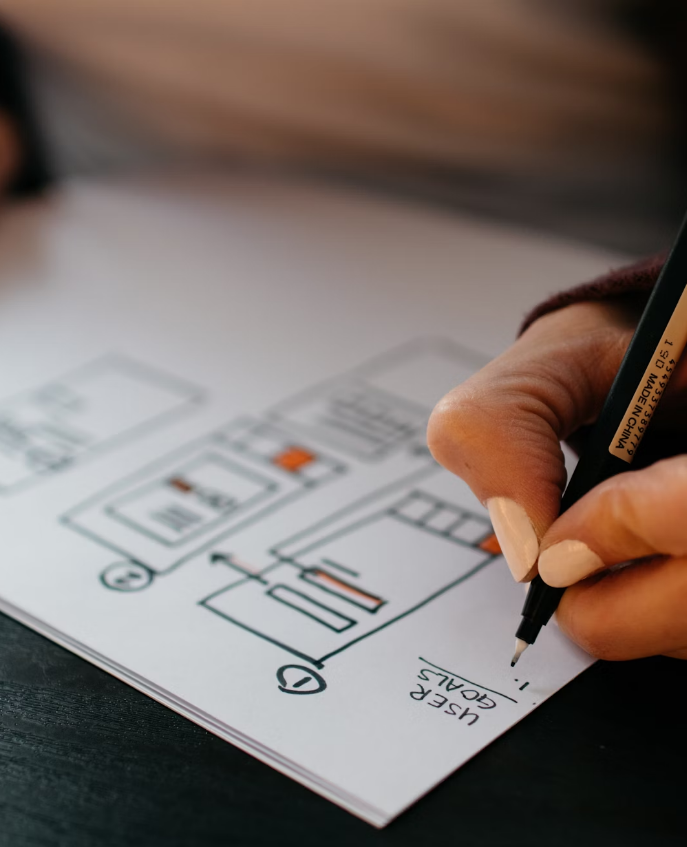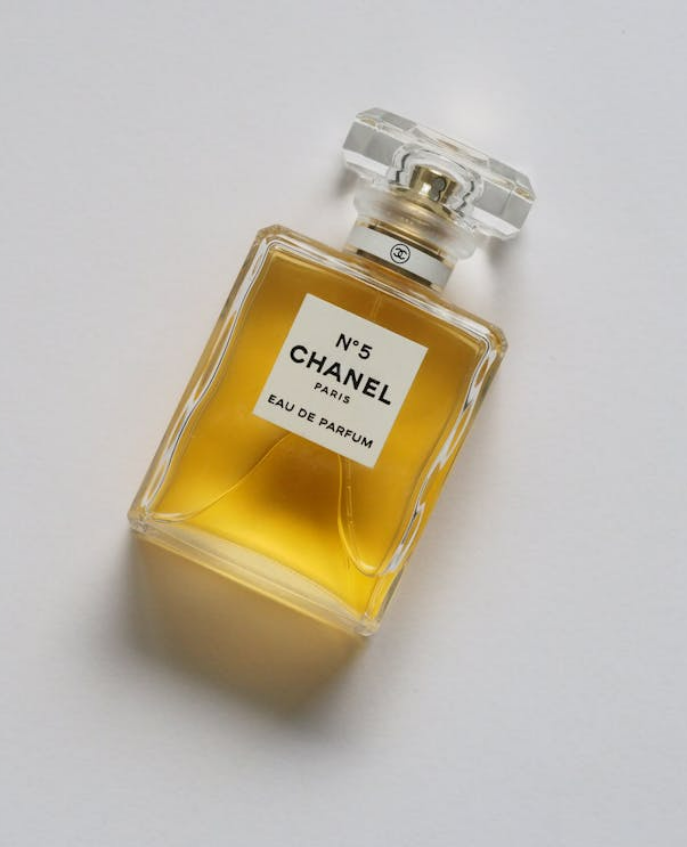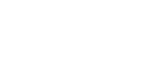ITシステム開発の各現場では、要件確認ならびに仕様確認という二つの重要な工程が、プロジェクト全体の成否を大きく左右しています。
プロジェクトを確実に成功へ導くには、ユーザーや関係者の要求を徹底的に理解し、明らかにされた要件を定義したうえで、具体的な仕様を丹念に整理しておくことが不可欠です。
これらの工程が曖昧なまま進行してしまうと、その後の開発フローで混乱が生じ、予定されていた予算やスケジュールの遅延といったリスクが現実のものとなる恐れがあります。
この記事では、ITプロジェクト現場で注目すべき要件確認と仕様確認のプロセス、両者の異なる役割、実務での活用方法、現場ごとの進め方などを丁寧に解説します。
要件確認と仕様確認の重要性
ITプロジェクトでは、要件確認と仕様確認が特に重要な工程となります。
発注者と開発ベンダーが密なコミュニケーションを重ね、プロジェクト着手前に明快な要件定義を作成しなければ、期待通りのシステムが納品されない、あるいは実際に業務で使われない余計な機能が生まれるなど、さまざまな問題が起こりやすくなります。
要件の誤認識や不足は、スケジュールの遅延やコスト増大を招き、プロジェクト全体にネガティブな影響を及ぼします。
特に他社や外部ベンダーにシステム開発を依頼する場合は、事業内容や各現場の業務プロセス、さらに関連する暗黙ルールに精通した信頼できるパートナーを選ぶことがプロジェクトの成否を左右します。
そして要件取りまとめという工程を十分に重視し、具体的な業務とシステム利用者のニーズ、必要な機能を現実的な観点で整理していく必要があります。
こうした細かな確認がなければ認識齟齬や追加開発、最悪の場合はプロジェクトの頓挫につながりかねません。
徹底した要件確認・仕様確認、効率的な工程管理を意識すれば、結果的にプロジェクトの成功率は大きく向上します。
要件確認・仕様確認は、プロジェクト成功率を高めるために不可欠な工程といえます。日本情報システム・ユーザー協会が実施した調査によると、システム開発における工期遅延の主な原因は要件定義フェーズにあることが明らかになっています。
実際、全体の4割近いプロジェクトが、要件定義段階での問題によってスケジュール遅延を経験しています。
要件定義は開発初期の最も重要な段階に位置づけられ、ここでの抜けや漏れ、あるいは曖昧な表現があると、その後の設計や開発で手戻りが発生し、追加コストや開発工数の拡大につながってしまいます。一方、要件定義を計画的かつ適切に遂行すれば、設計・実装・運用までの各工程がスムーズに流れ、全体効率や製品品質の向上へと結びつきます。
このような背景から、要件確認・仕様確認の徹底は、ITプロジェクトの効率化および品質向上、リスク低減に不可欠であると強調できます。
要件確認と仕様確認の工程
ITシステム開発の現場において、要件確認と仕様確認は複数の工程によって体系的に進められます。
第一に、要件定義書の作成が必要となり、システム導入の目的や業務における要望、システム化する範囲、各要素の優先順位を明確に整理します。この段階では業務フローや機能要件を一覧にし、現状業務の課題や改善点を把握したうえで、期待される性能や利便性、セキュリティ要件を盛り込みます。
次いで、基本設計工程では定義した要求や機能に基づき、具体的な仕様や動作内容をまとめます。システム構成や外部インターフェース、使用技術・ツールも具体化し、詳細設計でさらに仕様を細かく分解、技術者との適切なすり合わせを繰り返します。
テスト工程では、要件と仕様に応じたテスト項目を設定し、機能・性能・運用面で期待値が実現できているか最終確認します。各段階で効率的な確認とドキュメント管理を意識することが、システム開発全体の成功に直結します。
要件確認から仕様確認までの標準プロセスは以下の流れに沿って進めます。
- 要求収集:ユーザーや現場担当からヒアリングし、業務フローや現在のシステムを調査します。
- 要求分析:集めた情報を分類し、優先順位や実現の可否を冷静に評価します。
- 要求定義:分析結果にもとづき、システム化するべき内容や業務要件を明文化します。
- 要求仕様記述:定義した内容を詳細化し、要求仕様書という形でドキュメント化します。
この一連の流れにおいては、全体像と業務要件を常に意識し、関係者との合意形成と認識合わせを丁寧に進めることが品質向上につながります。また、設計や開発など後続工程への悪影響を未然に防ぐ意味でも、各段階で十分な確認や調整を怠らないことが肝要です。
要件確認と仕様確認の必要スキル
要件確認と仕様確認を担う担当者には、幅広いスキルが求められます。特に重視されるのは、業務内容やプロジェクト全体を俯瞰的に理解し、ユーザーの要求を論理的かつ抜け漏れなく整理する能力です。また、ITやシステムの用語、基本設計知識や調査・ドキュメント作成のスキルが不可欠です。重要なスキル領域としては、
- 要件整理力
- 合意形成・調整力
- 全体を幅広く見る俯瞰力
- 関係者間の円滑なコミュニケーション力
などが挙げられます。さらに、現場での設計・開発経験があれば、より実践的な仕様策定も可能となり、経験や知識の蓄積が大きなポイントとなります。
要件確認のプロセス
ユーザー要求を要件定義に落とし込むプロセスは、まず現場の理解から始まります。
ヒアリングや業務フロー分析を通じて、ユーザーの本質的要望や業務の実態を深掘りし、どの機能やサービスが本当にシステム化すべきかを整理します。
次に、抽出した要望を項目ごとに明確化し、システム導入の目的や優先順位、利用ケースを明らかにします。この過程で曖昧な表現は避け、現場の専門用語を正確に理解して記載することが、効率的な要件整理と合意形成につながります。
要件定義ドキュメントには、機能要件はもちろん、運用・セキュリティ・性能・外部連携といった非機能要件も必ず盛り込むことが大切です。関係者間の情報共有や継続的なフィードバックの反映も成功のポイントとなります。
ユーザーからのヒアリングで収集した要望・要求事項は、段階を踏んで整理し、ドキュメント化します。最初に業務の現状や抱えている課題を可視化し、要求事項の優先度や実現性について関係者と認識合わせを行います。
続いて、各要件ごとに目的・必要な機能・仕様を具体化し、重複や漏れがないか何度も見直します。認識齟齬を予防するため、ユーザーに納得感のある説明資料の整備、必要であればサンプル画面や類似事例の提供も有効です。
要件の一覧化やフロー整理を図り、後続工程へのスムーズな引き継ぎも意識します。
要件書の作成
要件定義書の作成では、システム開発全体を見通し、過不足なく必要項目を網羅することがとても重要です。
定義すべき基本項目には、以下の内容が含まれます。
- システム導入の目的と業務背景
- 適用する業務範囲とユーザー要求一覧
- 機能要件・非機能要件(性能、セキュリティ、外部連携など)
- システム構成や既存システムとの関係性
- 運用・保守方針
単なる要求事項の羅列に終始せず、現場担当や利用者と何度もヒアリング・確認したうえで、活用シーンや業務フロー、検討ポイントもあわせて整理します。
また、要件定義プロセスや意思決定の経緯をドキュメント化しておくことで、後の設計・実装・運用工程で認識齟齬や課題発生を予防できます。要件定義書作成は、プロジェクト成功を左右する基礎作業であることを意識しましょう。
要件確認の目的
要件定義書と仕様書は目的や記載対象が異なるため、それぞれの特性を理解することが重要です。要件定義書には、利用者からの要求や期待される機能、運用・管理要件、性能・セキュリティ・拡張性など非機能要件、さらに予算やスケジュールなど企業が求める制約事項を記載し、プロジェクトの全体像を整理します。
仕様書は、その要件定義を受けて具体的な動作・設計を記載するドキュメントです。要件定義書作成時は、仕様書で決めるべき内容と要件で明らかにしておくべき内容の区別を意識し、両者に抜けや重複がないよう注意します。
プロジェクト目的や関係者の要望、実現可能性を正しく整理し、要件定義書がシステム開発のベースラインとしてしっかり機能するようにすることがポイントです。
仕様書作成のプロセス
仕様確認時に確認すべき詳細項目は多岐にわたります。
まずシステム要件の背景や目的、基本機能や業務フローを明文化し、利用者と開発側が共通認識を持つことがスタートラインです。
設計段階では、ユーザーインターフェース設計や外部サービス連携、セキュリティ設計、データベース構成、インフラ要件などを個別ケースごとに具体化します。
非機能要件としては、求められる処理性能や拡張性、運用性、障害時対応策、アクセスコントロールや監査記録なども検討します。
テストシナリオや運用設計も仕様確認時点で整理しておくことで、全体工程の進捗や品質管理も飛躍的に向上します。業種やシステム規模による違いを意識し、仕様確認時は各要件を丁寧に検証・記載することが極めて重要です。
性能、セキュリティ、外部サービス連携など仕様確認に必要なチェックリストの作成では、現場からの要求を体系立てて整理し、機能要件・非機能要件ごとにポイントを明確にします。ヒアリングや業務分析で現状の課題や既存システムの問題点を探り、必要な要件を洗い出します。
性能面では応答速度や処理能力、可用性、拡張性などの具体的な数値目標を、セキュリティ面ではアクセス管理や情報漏洩防止、ログ管理などを検討します。
外部サービスとのインターフェース設計や運用時の課題解決策にも目を配り、開発側とクライアント双方に認識のズレが生じないよう配慮します。
ときにはクライアントが機能面にばかり注意を向けがちですが、非機能要件も意識的に加味することで、システム全体の満足度や価値が飛躍的に向上します。
要件確認・仕様確認フェーズでは、抽象的な要望や関係者間の認識齟齬、優先順位の不明確さ、リスクや制約条件の整理不足など、典型的な課題が浮かび上がることがよくあります。
特に要件定義の時点で目的や全体像が曖昧なまま進んでしまうと、設計や開発で大規模な修正・追加工数が発生するリスクが高まります。
- 要件・目的の明確化
- 利用部門との認識合わせ
- 検討事項の一覧化と優先順位付け
- リスク・課題の早期発見
- ドキュメントによる合意形成
など、着実な管理手法と効果的なプロジェクトの進行を実現することが品質向上につながります。現場担当との密な連携、定期的な進捗確認・意見交換も大変重要な要素です。
失敗事例
現場でよく見られる要件確認・仕様確認における失敗事例としては、要件に対する認識違いや合意不足、ドキュメント不備、現場のニーズの吸い上げ漏れ、目的やスコープ設定があいまいによる手戻りなどが指摘されます。
一方、成功事例では全体プロセスを強く意識し、ユーザーおよび経営層との十分なコミュニケーション、業務理解、合意形成、各工程での課題抽出・解決策検討を繰り返しています。
たとえばIPAのガイドでも、
- 目的・ゴールの明確化
- 関係者間の用語・要件内容認識合わせ
- 優先順位・制約の明文化
- 必要に応じて目的や課題の再整理
などが高品質な成果やプロジェクト成功の鍵であると述べられています。
失敗・成功のポイントをふまえて、効率的な要件管理やプロセス最適化に取り組みましょう。
要件確認および仕様確認工程は、システム開発プロジェクトの成否を左右する重要な鍵です。
特に若手エンジニアにとっては大きなチャレンジとなりますが、プロジェクト目標の達成のためには避けて通れないプロセスです。
経営層やユーザーからの要求を正確に把握し、きちんと設計工程に落とし込むには、全体的なフローと注意すべきポイント、必要ドキュメントや業務知識、合意形成の方法などを意識して実践することが重要です。
本記事で解説した考え方や進め方をぜひ参考に、現場での要件定義・仕様確認工程に取り組み、優れたシステム導入・成果の実現を目指してください。実践として次のプロジェクトから取り入れることをおすすめします。